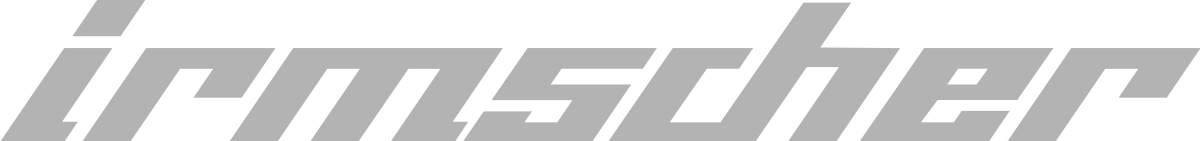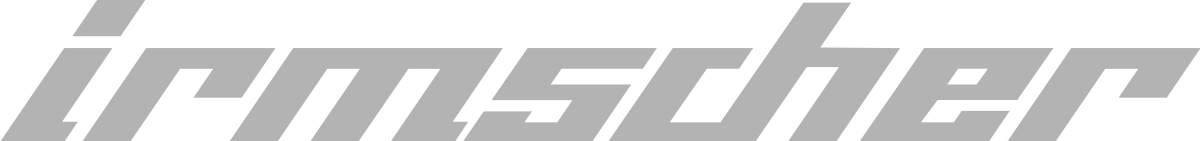ただ上に積み重ねただけでは、絶対このように一台一台を隅々まで鑑賞出来るように満遍なく照明が当たることは無かったと思います。
そしてさらに前後左右の限られたスペースにもピタリと収まっています。
この画像ではまだ背後に以前紹介しましたジッポーライターの入った10㎝×10㎝×10㎝ガラス水槽が置いてありませんが、それを元に戻すと前後のスペースもギリギリになります。
2023年3月12日
すでに上述していますとおり
OPEL KADETT B ラリー仕様のミニカーではなく、私の愛車
ISUZU Gemini ZZ-R coupé PF60の正真正銘兄弟車たる
OPEL KADETT GT/E ラリー仕様を購入しようと、
eBay USAを探しました結果、まずこのスクショのモデルを購入しました。
実は
OPEL KADETT GT/E ラリー仕様を探すに当たって、グループ
1orグループ
2/
4で随分迷いました。
何故かと申しますと、グループ
1とトップカテゴリーのグループ
4では競技大会やドライバーの知名度が大違いで、例えばドライバーで云うとオペルカデットグループ
4には
ハンヌ・ミッコラや
ワルター・ロールなど名だたる世界的ラリードライバーのマシンが出てくるのですが、一方グループ
1のモデルと云えば、ほとんどがローカルラリーレベルで年代が古いとはいえご当地有力ラリードライバーばかりで、正直に申しますと初めて知るドライバー名ばかりでした。
そんな中で唯一このスクショにあります
ミキ・ビアシオンの名前だけはとても良く知っておりましたし、親しみもありました
(歳が一っこ下)ので購入することに決めました。
では何故グループ
1にしたのかと申しますと、グループ
4の戦闘的な迫力のあるオーバーフェンダーのスタイルも充分に魅力的なのですが、我が
PF60の兄弟車としてその特徴とも云える、流麗で美しいクーペボディを伝える意味においては、むしろオリジナルに近い改造範囲の狭いグループ
1仕様の方が良いと判断したためです。
また様々なカラーリングの同競技車があったのですが、そこは敢えて
OPELの最も代表的なフラッグカラーでもあるホワイト&イエロー+ブラックを選択しました。
と云うよりもむしろ、私の1980年代の記憶に強く残っています
OPEL KADETTのヨーロッパラリーにおけるイメージカラーが、このホワイトとイエローのツートンカラーであったと言うのがより正しい認識だと思います。
このサイトでも度々登場している当時の画像です。
特に注目して頂きたいのは、まんまヤンキーのとっぽい私では無く、
PF60の
ドアミラーと
irmscher純正の
16インチアルミホイールの方です。
まだこの頃の国産車はそのほとんどが、この
PF60も含めて純正はフェンダーミラーでした。
そこで
青山ピットインで
OPEL純正のドアミラーを購入し、ご覧のように取り付けていました。
純正フェンダーミラーの取り付け穴は、溶接板金して塞いでいました。
次に最上段の棚の支柱となる部分を折り曲げます。
この画像は2回目のヒーターを当てているところです。
展示場所としてはここで良いのですが、予定ではもう一台購入しているOPEL KADETTの到着が遅れていますので、それが届くと同タイプのディスプレイケースを3台積み重ねることになります。
しかしこのまま単純に3台積み重ねるのは少し無理があるだろうと感じています。
もしもあまりに不安定なときには、特別に専用のディスプレイスタンドを自作するつもりです。
さぁて試しに三個のディスプレイケースを載せてみましょう。
ご覧の通り2枚の棚板はディスプレイケースの台座のサイズとピッタリ同じサイズです。
一番下のディスプレイケースは床に直接置いているだけです。
つまり自作しましたディスプレイスタンドは、上の2つのディスプレイケース専用のスタンドだと云うことになります。
ところが一番下のディスプレイケースを置くことで、バランスの取れた三段重ねのディスプレイが完成するということがこれでお解りになるかと思います。
まさに狙い通り効果的かつこの場所にドンピシャのディスプレイスタンドになりました。
しかもちょっと見た目には、上の2台のディスプレイケースは宙に浮いているように見えて、よく観察しないとこの仕組みは判らないと思います。
また余談ですがこのページの上で紹介していました、ピエロ・リアッティがドライブしサンレモラリー1995で総合優勝しましたSUBARU Impreza WRC A.R.T. Engineering仕様CarNo.⑥のTrofeu 1/43 MinicarがKadettの右側に確認出来ると思います。
右の画像がそのMinicarの拡大画像です。
そして日本では
金子繁夫らトップラリーストによって、
ISUZU Gemini ZZ-R coupé PF60が全日本ラリー選手権で大暴れしました。
さてではこの
OPEL KADETT GT/E グループ
1はと云えば、
COPPA CITTÀ DI MODENA 1979 第8回 ラリー・チッタ・ディ・モデナ 1979と、
38. Italy Nazionale シティ・カップ・オブ・モデナ
1979 第38回 イタリアラリー選手権の両タイトルが掛かったイタリア国内のローカルラリー選手権に出場したクルマです。
そしてドライバーは、
1988年に
ランチア・デルタ・インテグラーレに乗り、出場した
7戦中
5勝を挙げて
WRC初タイトルを獲得し、
1989年の世界ラリー選手権も出場
6戦中
5勝を挙げタイトル連覇を達成した、
マッシモ・「ミキ」・ビアジオン(伊) Massimo 'Miki' Biasionです
。
このように限られたスペースにどうすれば効果的な展示が出来るのかあれこれ考えたり工夫したりすることは、知恵の輪を解いたりパズルを埋める作業よりも、私にとっては遥かに楽しい頭の体操です。
そして実際に予想通りの結果が得られたときには、何ものにも代えがたい喜びがあります。
今回もそういう案件のひとつでしたが、私のガレージは当にそうしたサティスファクションに溢れています。
つまりこのMiniatur Carはラリー史に足跡を残した貴重なドライバーと車両だったということになります。
そして一方このVITESSE(ビテス)というミニカーブランドですが、1/43スケールのコレクターの間では有名な、80年代初頭に誕生したポルトガルのブランドで、ビテスはミニカーマニア(特にラリーカー)向けの商品を手がけていました。
複数のブランドをかかえていた人気メーカーでしたが、2000年に経営破綻しており現在は中国のixo(イクソ)がビテスグループを受け継いでいます。
しかし現代の自動車は時代の様々な要求に答え、ついにはガソリンエンジンすら完全に否定されつつあります。
こんな時代だからこそかつてガソリンエンジン全盛期だったころの自動車に憧憬の念を抱いてしまうのは仕方の無いことではないでしょうか。
このOPEL KADETTにしましてもGM のグローバルカー構想に則って産み出されたと前述しましたが、まさに当時最先端の時代のニーズに応じて誕生した自動車だったのですから。
これはブリスターパッケージの裏面です。
ここにもメイドインバングラデシュと明記されています。
さらにOPELの正式ライセンスを得ている旨も記載されています。
さてこのOpel Kadett C GT/E Team Irmscher Rally Hunsruckですが、Rallye Monte Carlo 1978 OPEL KADETT GT/Eを注文した同日に注文していました。
到着までに掛かった時間は倍以上でしたが…
そしてRallye Monte Carlo 1978 OPEL KADETT GT/Eは文字通りモンテカルロラリー出場車という理由で購入したのですが、このOpel Kadett C GT/E Team Irmscher Rally Hunsruckを購入したのにもハッキリした理由がありました。
これをご覧下さい。
ダストカバーをミニカー台座にセロテープで固定することはこれまでにもありましたが、台座に固定されているミニカーを台座ごとラップで縛るように巻いてさらに厳重に固定しています。
ここまで輸送に配慮した梱包は初めてでした。
これだけしっかりと内容物が固定されていれば配送業者側にとっても安心出来ますね。
それは単なる自己満足の賜ですが、敢えて賜と呼ばせて頂きたいと思います。
これで魅力的なアイテムがまた一つこのショーウインドーに加わったことは確かです。
そしてこうして斜め45°前方から見ますと、どうしてこのような形状のスタンドにしたのか、その意図は明白だと思います。
下へ行くほどディスプレイケースが半分づつ前に迫り出すよう展示出来る造りになっています。
実はこれがディスプレイスタンドを自作しました一番大切なポイントで、手前味噌ではありますがちょっと他人にはマネの出来ないオリジナリティー溢れるアイデアスタンドだと自負しています。
自画自賛で恐縮ですがとても美しい出来映えだと思います。♪
これで完成です。
後は例によってサンドペーパーで折り曲げた背の部分の凸凹を修正し、専用研磨剤で磨くだけです。
念のために一段目の棚も再度チェックしました。
問題ありません。
折り曲げ作業が終わりましたので、最上段の棚の水平をチェックしました。
前後にほぼ水平であることを確認しました。
ひとつ前の作業と同様に、直角定規を当てて角度を固定しています。
2回目のヒーターを当てています。
最後に最上段の棚部分を直角に折り曲げます。
裏返しまして2回目のヒーターを当てています。
これも最初の折り曲げ作業と同様に、両面から充分に熱を加えました。
続きましてクランク状に折り曲げてディスプレイスタンドの底面を作ります。
一回目のヒーターを当てています。
まず最初に一段目の棚になる部分を折り曲げます。
この画像は1回目のヒーターですが、この部分は120°以上角度を付けて折り曲げなければなりませんので、やや長めにヒーターを当てて充分に熱を加えておきます。
この後実際に曲げる背の部分に2回目のヒーターを当てますが、一回目に剥がしたペーパー(弱粘着性があります)は元に戻します。
それは2回目にヒーターを当てるときの目印にするためです。
その間少しの時間(10秒くらい)であれば熱が冷めてしまうことはありません。
次に全体の長さ(453㎜)を決めてカットし、折り曲げ線を両面に引きました。
2023年4月10日
これでOPEL KADETT C RALLYのミニカーが3台揃いました。
談話コーナーのショーウインドーに飾るため3台のディスプレイケースをそのまま重ねようと試みましたが、やはり不安定で3台のディスプレイケースを水平に保つにはかなり無理があるようです。
ご覧頂くと判りますように、ステアリングホイールのコーンが浅いタイプにフィットするようです。
一般的なオールドタイプのスリースポークスポーツステアリングホイールであればほとんどが装着可能です。
そしてパッドの裏側の中心部は、丁度ホーンボタンに接触し易いよう凸型に成形されています。
それからまだ確か取っておいたはずだと倉庫を探しましたら、案の定このirmscher純正ステアリングホイールパッドが出て参りました。
やや硬めのウレタンラバー製で、取り付けは市販のスポーツステアリングホイールの上からスッポリ被せて使用します。
たぶんこんなものでもヤフオクなどに出品すれば幾らかの値は付くと思いますが、私はそんな野暮なマネはしません。
つまりこのキャリングボックスと同様、決して大袈裟でもなんでも無くこれはアールエーアール鈴鹿の歴史そのものなのですから。
それにしてももっとちゃんと貼れなかったのか(笑)
さて遅れましたがこのOpel Kadett C GT/E Team Irmscher Rally Hunsruckを紹介します。
ドライバーはAchim.Warmbold アビム・ウォームボールド(独)17.7.1941生(81歳)、コドライバーはWilli-Peter Pitz ピッツ・ウィリ・ピーター(独)22.5.1951生-23.10.2018年没(67歳)です。
第11回 AvD/STH-フンスリュック・ラリー(独) 1978年に、Opel Euro Händler Team オペル ユーロディーラー チーム(チーム イルムシャー)から出場しました。
因みにフンスリュック・ラリーとはヨーロッパラリー選手権の掛かったドイツ国内のフンスリュック山地を中心とした山岳ローカルラリーのことです。
例えばこのラリー仕様にも着いています、リアトランクのイルムシャー純正ラバーリップスポイラーや、OPEL純正のドアミラーなど他にも色々とirmscher純正パーツをジェミニZZ-Rに装着していました。
この後もっと詳しく触れたいと思います。
それもただ知っていたと云うだけでは無く、当時の私の愛車ジェミニZZ-RにはOPELやirmscherのパーツを積極的に装着しておりました。
このパッケージはとても魅力的なデザインだと思います。
特に渋くシャープなカラーリングに加えて、正面と車両前方をひとまとめにした小窓の処理と工作は秀逸な出来映えです。
このように商品は見せる工夫が大切だと思います。
このエアーキャップシートも緩衝材の定番です。
2023年3月19日
この日eBay USAにて注文し、後に3月22日に発送との連絡を受けました。
但し追跡番号が付されていなかったため、発送連絡後のトラッキング情報がまったく得られませんでしたので、ただ荷物の到着を待つのみでした。
これまでにも幾度か追跡番号が付されないことがありましたし、追跡番号が付されていても番号が間違っているのかどうかは判りませんが、荷物の追跡が出来ないこともありました。
そういう場合はたぶん国際郵便による郵送ではなく、Shopあるいは個人的に委託した配送業者等による場合など様々なケースがあるのだと思います。
今回はEnvío internacional estándars(標準国際配送)とありますが、配送業者は明示されていませんでした。
発送元はスペインです。
まぁパッケージングやメーカーの話は横に置きまして、製品をパックから取り出しました。
上に紹介しましたOPEL KADETT GT/E ラリーグループ1ビアシオン仕様と同じシリーズだと思われますが、先に紹介したミニカーはオリジナルブリスターパックから取り出された状態で届きましたので、確たることは申せません。
さらに申し上げるとこの商品も上記のベンツとルノーのMichelinサポートビークルも、製造は同じバングラデシュです。
ixoは香港のミニカーブランドですが、どういうシステムでミニカーが製造されどのように流通しているのか一度調べたいと思っています。
早速梱包の段ボール箱を開けました。
両更クラフト紙とエアーキャップシートの緩衝材でしっかり梱包されていました。
2023年3月27日
実はこの日上に紹介しましたOPEL KADETT GT/E ラリーグループ1ビアシオン仕様の他にもう一つ荷物が届いておりました。
実はこのMiniature Carを購入しました当時(1990年代)から、私はジャン・ラニョッティというフランス人ラリードライバーの名前はよく存じておりました。
詳しくは後述します。
そして今回調べた結果、このラリーカーはラニョッティが国際格式のラリーに初出場したときの記念すべき車両であることが判りました。
2014年4月4日
かつて

のページでチラッと紹介しましたこの画像ですが、そのときの記述でアールエーアール鈴鹿にとってはとても重大な錯誤がありましたことをここに報告します。
それは画面左下に見えます
OPEL KADETTの記述に、私の二代目の愛車
ISUZU Gemini ZZ-R coupéの兄弟車と記していましたが、それは画像の
OPEL KADETT type Bではなく
OPEL KADETT type Cのことです。
気にはなっていましたが、同じ
OPEL KADETTということで今日までずーっと目をつぶって参りました。
ビアシオンの全盛期とも言って良いランチアワークス時代のチームメイトとしては、後に
SWRT(SUBARU WORLD RALLY TEAM)黎明期のワークスドライバーとして活躍しました「無冠の帝王」と呼ばれた
マルク・アレンや、
TOYOTAワークスの
TTE(TOYOTA TEAM EUROPA)セリカツインカムターボで活躍した
ユハ・カンクネンが居ました。
因みにこの
OPEL KADETT GT/E ビアジオンモデルは、ビアジオンが公式ラリー競技に初参加したときの記念すべきラリーカーです。
HAWK RACING CLUB Srl ホークレーシングクラブ
Srlというプライベートチームから出場しています。
私も当時
(ランチアワークス)その圧倒的強さを誇ったミキ・ビアシオンをハッキリと覚えていました。
イタリアではその偉業のため現在でも英雄的なラリードライバーとして語り継がれています。
WRCを離れた後はイタリアのタイヤメーカー、ピレリの開発ドライバーを務めたほか、ラリーレイドの三菱のワークスドライバーとしてダカールラリーや
UAEデザートチャレンジなどに参戦しました。
こちらに
マッシモ・「ミキ」・ビアジオンMassimo 'Miki' Biasion の
WEB SITEを掲載しておきます。
言い換えればミキ・ビアシオンは
WRCドライバーズチャンピオンを2度獲得した、唯一無二の偉大なイタリア人ラリードライバーと云えるでしょう。
さらに彼のマシン調整能力はあの
カルロス・サインツや
ディディエ・オリオールと並び称されるほど評価が高く、後にランチアワークスからフォードに移籍したとき、組織風土の違いからフォードチームとの関係がギクシャクし満足な成績を残すことが出来なかった話は有名です。
またコドライバーの
ティツィアーノ・シビエロ(伊) Tiziano Sivieroですが、このラリー・チッタ・ディ・モデナ
1979 から
1995年に
WRCを事実上引退するまで、全てのラリーでビアジオンのコドライバーを務めました。
左の当時の私と愛車PF60のツーショットですが、フロントスクリーン越しに左Aピラーの室内側に何やら不思議なものがぶらさがっているのが確認いただけると思います。
それが上の2点の画像にあるバトラー製フレキシブルマップランプだと判る方は、そうとうのラリー通かマニアだと思います。
コドライバーのためのマップ見用のスポット照明ですが、こんなものを取り付けていることからもアールエーアール鈴鹿が当時から熱烈なラリーファンであったことがお判りになると思います。
私の愛車にはこのとき
italvolantiのステアリングホイールが着いていましたので、ホーンボタンが当時一般的なホイールの中心部になかったためこのパッドが使えませんでした。
そこでやむを得ず
PERSONALだか
ABARTHだかは忘れましたが、わざわざセンターホーンタイプのステアリングホイールに交換し、
OPELのホーンボタンを取り付けて、この
irmscher純正ステアリングホイールパッドを装着していました。
上から3枚の画像は、右本文でも紹介していますTrofeu 1/43 Minicar サンレモラリー1995総合優勝 SUBARU Impreza WRC A.R.T. Engineering Piero Liatti仕様CarNo.⑥モデルを詳しくお伝えしようと単独撮影した画像です。
流石にWRCチャンピオンともなると、ちょっと探せばその画像に困ることはありません。
数あるミキ・ビアシオンの活躍の中でも最も輝かしい画像を選びました。
一番下の画像は当時のワークスランチアのチームメイト。
左からユハ・カンクネン、マルク・アレンそしてミキです。
ジャン・"ジャンノ"・ラニョッティ Jean "Jeannot" Ragnotti
1945年8月29日生(77歳)
現在はルノーの名誉広報部長を務めており、ルノーや自動車専門雑誌などのイベントのゲストとしてたびたび来日しています。
そしてそのピエロ・リアッティの1995年サンレモラリーでの勇姿が上の2枚の画像です。
因みにこのミニカーは以前から所有しています。
そしてその賜はこれからも進化増殖し続けると思います。
さらにこちらにも別タイプのirmscherエンブレムが貼ってあります。
確かコレの方が先に紹介したものよりも後に購入したものだったと記憶しています。
なんとも勿体ない使い方だとは思いますが、当時はエンブレムをこれ見よがしに愛車に貼るのはあまり好みでは無かったのです。
あいにく走行シーンの画像は見つかりませんでしたが、それよりもっと貴重なこのフンスリュック・ラリーにおけるこのカーナンバー③のサービスシーンの画像を見つけました。
どうやら手前の紺色のチューリップハットを被った人物が、ドライバーのアビム・ウォームボールドのようです。
いずれにしましても当時の西ドイツのローカルラリーの雰囲気が良く出ていると思います。
上の2枚の画像は、イタリア北部のルイジ・ボンファンティ-フィマール自動車博物館の企画展にて撮影されたものだそうで、まさにミニカーの実車です。
つまりミュージアムに展示されるほどイタリア国内では未だにミキ・ビアジオンは人気があるという証明でもあると思います。
尚、これら2枚の画像は、2016年1月13日にWEB CARTOPに寄稿されたモータージャーナリスト原田了氏撮影による貴重な画像をお借りしました。
話を本題に戻しましょう。
このMiniature CarはOpel Kadett GT/E Rally Of Modena 1979 'Miki' Biasion グループ1仕様です。
ラリー競技車両とは云っても、安全装備を除いては限りなくノーマルの市販車に近いモデルです。
それだけにノーマルの素性の良さがそこかしこに表れていると思います。
このページでこれまでに紹介しました2体のコレクションと同型のディスプレイケースですが、このモデルはパッケージとは対照的に派手さの無いとてもシンプルで抑制的な意匠です。
私はむしろこの方が好みです。
この場合は断面図に照らして角度を決めるのでは無く、一段目の棚にこのように水準器を置いて水平を確保しながら折り曲げ角度を決定し固定しました。
この曲げ角度は正確に何度なのか測っていませんので判りませんが、こうして断面図に直に照らし合わせますので角度不明でも問題はありません。
完全に熱が冷めるまではしっかりと角度をキープホールドします。
熱が冷め切らぬうちにホールドを緩めてしまいますと、若干戻りがありますので要注意です。
向かって左側がスタンドの一段目になります。
切り出したアクリル板の切断面を平滑にします。
アクリルカッターの切削ブレードを使って、切断面を少しづつ削って平らになるように整えます。
まずは3㎜厚のアクリル板を規定の幅(151.5㎜/デイスプレイケースの幅)にカットします。
2023年4月11日
本日は3台のOPEL KADETT C RALLYのディスプレイケースを重ねて安定的に展示するための無色透明3㎜厚アクリル板ディスプレイスタンドを製作します。
いろいろな加工法をじっくりと検討した結果、1枚のアクリル板を曲げ加工だけで製作するのが、この場合最もシンプルでスマートな方法だと判断しました。
その方法を実践するには出来るだけ正確な曲げ加工用の実物大断面図が必要です。
実際にホーンを鳴らすときには、パッド中央部分のiマークをやや強く押せばOKでした。
加えてソフトなウレタン成形品であるため、衝突時などの衝撃吸収性、安全性にも寄与する優れたパーツでもあります。
とまぁこんな具合に当時は相当irmscherに拘っていたのが解っていただけたかと思います。
それだけ良質の作りと材質の製品だったということです。
事ほど左様にアールエーアール鈴鹿の物に対する拘りや価値観は、当時から今日に至るまでまったく変わっていないと云う証だと思います。
そしてここで紹介したいのはこのirmscherのエンブレムです。
折角購入(何処で入手したのか忘れました)したのに結局愛車には貼らずに残ってしまいましたのでここに貼りました。
それはOpel Kadett C GT/E Team Irmscher Rally Hunsruckのタイトルにもあります通り、Team Irmscherの名称に高い関心があったからです。
かつてのいすゞジェミニをご存じの方でしたら、FFになってからの二代目ジェミニにイルムシャーというモデルがあったのを覚えている方もいらっしゃるでしょう。
私は初代ジェミニZZ-Rクーペ(新車購入)に乗っていた当時から、オペルのチューニングファクトリーであるirmscherの存在はよく存じていました。
それらセロテープやラップなど固定物を全て取り去りました。
Opel Kadett C GT/E Team Irmscher Rally Hunsruck A. Warmbold - W.Pitz 1/43 ixo
とは言うもののこのページで紹介したものの中にも実際にフランスからは一週間で届いています。
望むらくは世界のどの地域からでもその程度の日数で届いて欲しいものです。
さてこの荷物はご覧のようにとてもしっかり梱包されていました。
2023年4月7日
本日到着しました。
発送連絡から優に2週間以上掛かりました。
もっともこれまでにもユーロ圏からは色んな物を購入してきましたが、中には一、二ヶ月以上掛かった物もありました。
ですから2週間程度の輸送時間はさしたる問題ではありません。
当時の雑誌か何かの見出しのようです。
"A MODENA VINCE SIMONTACCHI E DEBUTTA BIASION"
「SIMONTACCHI がモデナで優勝し、BIASION デビュー」とあります。
因みにSIMONTACCHIとはこのラリーにランチア・ストラトスHFで出場し総合優勝したラリードライバーのマウロ・シモンタッキ(伊)Mauro Simontacchiのことです。
これは当時のラリー専門誌なのかミニカー販売のカタログ冊子なのか良く判りませんが、この表紙の写真はまさにMiniature Carケースの背景画像です。
このディスプレイケースの背面にある数字の意味ですが、ラリーカーのスペックが記してあります。
1979立方センチはエンジン排気量、続いて4気筒、210cvのcvとはイタリア語Cavallo Vapore(馬蒸気)の略で、この場合210馬力ということです。
但しこの年代の馬力表示はグロス値ですので、現代のネット値に換算すると大体178.5馬力程度です。
因みに100cv = 100ps(hp)です。
最後のPirelliは説明不要ですね。
というわけで、このページにはまだつづきがあります。
取りあえず無造作に積み重ねてみました。
ただしケース台座の裏側の造形がこのように積み重ねることを想定していないのか、重ねた部分の据わりが微妙で安定していません。
この画像もまたモンテ名物雪のチュリニ峠だと思われます。
そしてまたPinterestにて画像検索しました結果、このMiniature Carの背景にも使われている画像が見つかりました。
因みにリヤフェンダーにconreroとありますのは、Conrero Squadra Corse コンレロ レーシングチームからのプライベート参加を表しています
残念ながらこのときまで私はこのドライバーもコドラも存じませんでした。
では何故詳細な大会リザルトや選手のプロフィールまで判るのかと申しますと、イタリアの
eWRC-results.com - rally databaseサイトで検索するとドライバーのプロフィール、戦歴とリザルトが詳しく載っていますので、私はそのデータを基本にしています。
https://www.ewrc-results.com/ ドライバーは
Federico.Ormezzano フェデリコ・オルメッツァーノ
(伊)です。
1948年
5月
21日生(
74歳)
そしてコドライバーは
Miniature Carには"
RUDY"とだけありますが、本名は
Roberto Dalpozzo ロベルト・ダルポッツォ
(伊) ニックネーム「ルディ」です。
御歳はドライバーより2つ年上です。
さてこのOPEL KADETT GT/E グループ1ですが、どういう車両かしっかり調べました。
まずこのラリーカーが出場した大会ですが、第46回 ラリー・オートモービル・デ・モンテカルロ 1978年 、WRC1978開幕戦モンテカルロラリーです。
リザルトはクラス2位、総合11位でした。
因みにこのページで紹介しているジャン・ラニョッティが駆るルノー5ターボが、このモンテで総合準優勝しています。
中身を取り出すと箱の底にShopのチラシが入っていました。
2023年3月27日
つまりこの荷物はわずか1週間で届きましたが、上の荷物は到着まで2週間以上掛かっていることになります。
イタリアとフランスそれぞれの郵便事情はどうなっているのか知りませんが、同じ国際郵便でありながらこの差はどう説明したら良いのでしょうか。笑
2023年3月19日
この日eBay USAにおいて左のスクショにありますRallye Monte Carlo 1978 OPEL KADETT GT/Eを購入しました。
発送元はフランスで翌日20日に発送されました。
もちろん現代車の方がボディ剛性や操縦性など優れていることは云うまでもありませんが、実質的にそれらの真価が問われるのはRALLYなどの極限性能が問われる極めて稀な場面においてだけでしょう。
当然それらの性能が高いに越したことはありませんが、クルマの基本性能などは実はこの時代にほとんど完成の域に達していたのでは無いかとさえ思うのです。
このシンプルかつとても美しいスラントノーズのクーペボディは、私は今の時代でも充分通用するカーデザインだと思います。
いやむしろこの方が現代車の複雑なデザインよりも遥かに洗練されていてムダが無いとさえ思うのです。
さらに私のようなSUBARU党にとって大変嬉しいミキ・ビアシオンのエピソードがこの画像です。
これは37. Rallye Sanremo - Rallye d'Italia 1995 つまり第37回サンレモ・ラリーにSUBARU Impreza 555を駆りA.R.T. Engineeringから出場し総合4位を獲得しましたミキ・ビアジオンです。
そしてこれを最後に長きに渡ったWRCから引退しました。
因みにこのラリーで総合優勝したのが、同じA.R.T. EngineeringからImpreza 555で出場しましたピエロ・リアッティでした。
マッシモ・「ミキ」・ビアジオン
(Massimo 'Miki' Biasion)
1958年1月7日生(65歳)
緩衝材の中から現れたのはコレだけです。
とても綺麗な状態です。
プライベーターらしくステッカーなどは実に少なく、如何にも若手新人ドライバーのデビュー戦といった感じです。
早速開梱すると発泡スチロールの緩衝材が箱一杯に詰め込まれていました。
これならば輸送中のショックにも充分に耐えられますね。
2023年3月27日
本日荷物が到着しました。
発送元はイタリアです。
この画像はその在りし日の画像です。
例のごとくPinterestを検索して見つけました。
すると様々なことが判ってきました。
まずこのOPEL KADETT B RALLYですが、1970年に開催されました39. Rallye Automobile de Monte-Carlo、つまり第39回 モンテカルロ ラリーに出場したモデルです。
ドライバーはJean Ragnotti ジャン・ラニョッティ(仏)、コドライバーはPierre Thimonier ピエール・ティモニエ(仏) です。
車両はグループ1で、このラリーでのリザルトはクラス優勝、総合11位でした。
2023年3月30日
しかしやはり厳密に言えば間違いであることに変わりはありません。
そこでこの際ここでその間違いを正すことにしましたが、その前にこのOPEL KADETT B ラリー仕様をしっかりと紹介しておきたいと思います。
購入しました当初はあまり深く考えずに購入しましたので、紹介するにあたりこのラリー車両のことをよく調べてみました。
ただ当時
KADETTはヨーロッパ圏の
RALLY競技では、
WRCのトップカテゴリーであるグループ
4では総合的にバランス良くなかったのかあまり活躍できず、後継の
OPEL ASCONA 400にその座を譲りました。
しかし下位のクラスではその後も長くプライベーターに愛され、当時ライバルであった
フォードエスコート2と熾烈なバトルを繰り広げました。
厚さが3㎜以上のアクリル板を曲げるときには、ヒーターを両面から当てた方が熱効率が高いので、このように両面に折り曲げ線を引いておきます。
3㎜厚のアクリル板の厚さを加味した上での、正確な寸法の曲げ加工実物大断面図です。
正確な寸法とは云えアクリル板の曲げ加工には誤差が生じるのも確かです。
そこで多少の誤差は許容範囲として容認出来るように寸法をはじき出したつもりです。
最も重要なことは一段目と最上段の棚のクリアランスが、棚にディスプレイケースを載せたときなるべく均等に見えることです。
これは実際に曲げ加工を実施してみないと何とも言えません。
加えて一段目とスタンドの底面が平行になるよう、曲げ加工の際に斜面のスタンド部分の角度が巧く決められるかが大切なポイントになっています。
ここが一番難しいところだと思います。
さてここからは少しの間アールエーアール鈴鹿の昔話にお付き合い下さい。
この画像中央の壁に掛けてある樹脂製キャリングボックス(パーツケース)にご注目下さい。
これもいすゞジェミニZZ-R PF60に乗っていたころ、かつて愛車のガレージとして使っておりました鉄骨スレート葺きの古いガレージ(この下方に紹介しているPF60の愛車と私のツーショット画像の背後に写っているのがその古いガレージです。今はありません)で重宝していたパーツ入れです。
かれこれ40年近く使っています。
2023年3月27日
その日のうちに所定の場所に展示してみました。
このデータ・ベースもそうですが、こうして当時のWRCなど主にヨーロッパのRallyの記録や画像などを調べていますと、つくづくモータースポーツ(特にRally)の歴史と文化が脈々と息づいていることを羨ましく思います。
改めて紹介します。
Rallye Monte Carlo 1978 OPEL KADETT GT/Eです。
何故このミニカーを購入したかと申しますと、比較的安価であったのと特にWRC出場車であったことが大きな理由です。
そしてグループ1仕様であり、OPEL KADETT GT/Eオリジナルカラーであることは言うまでも無いと思います。
これもPinterestで見つけた画像です。
モンテカルロラリー名物、雪のチュリニ峠でしょうか。
若き日のラニョッティです。
生涯を通してWRCでの戦績は3勝(トップカテゴリー)しか挙げていませんが、偉大なドライバーであることは間違いありません。
当時はラニョッティの名前と、OPEL KADETTのラリー車両だというだけで購入していましたが、結構特別な記録と内容を持ったMinicarだったと云うことが判りました。
それが今回調べてみて初めて知った事実です。
よく考えてみればラリーのモデルカーに、名も無きラリーストの車両などメーカーがモデルにする訳もありませんし、話題にも上らないラリーやドライバーなど対象にするはずもありませんね。
この部分は直角に立ち上げるだけですから、ご覧のように直角定規を当てて固定しました。
当時のモノだと証明する訳ではありませんが、かつてのLUCKステッカーが当時モノであると語っています。
たぶん当時津市内の国道23号線沿い津競艇場へ向かう直前右カーブの手前右側にあった輸入工具専門店(今はありません)で購入したと記憶していますが、ハッキリと覚えているわけではありません。
いずれにしましても樹脂製の造形物でこれほどの長い期間変質や変色、変形など何一つ問題が無いというのは本当に驚くべき耐久・耐候性だと思います。
さてここからが本ページの主題です。
左の画像が私が本来語るべき
OPEL KADETT C GT/Eです。
つまり愛車
ISUZU Gemini ZZ-R coupé PF60の兄弟車とも云うべきモデルです。
当時の
いすゞは市場性の見地よりベレットからのモデルチェンジを要望し、その結果資本提携していた
GMの「グローバルカー
(世界戦略車)構想」に基づき
オペル・カデット(
GM「
Tカー」)を
ベースに新型車を開発する事が決定しました。
その結果
1974年に
PF50、そして
1977年に
PF60が登場しました。
さぁ出ました、お馴染みのブリスターパックです。
ただしこのブリスターパックはミニカーケースごとパックされていますので何も問題はありません。
これは購入前にeBay USAの商品販売ページの画像で確認済みでした。