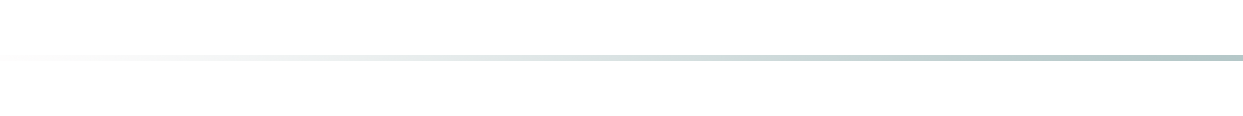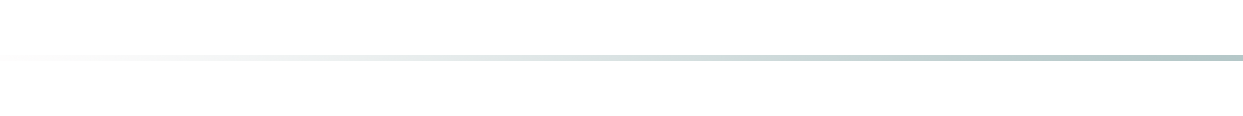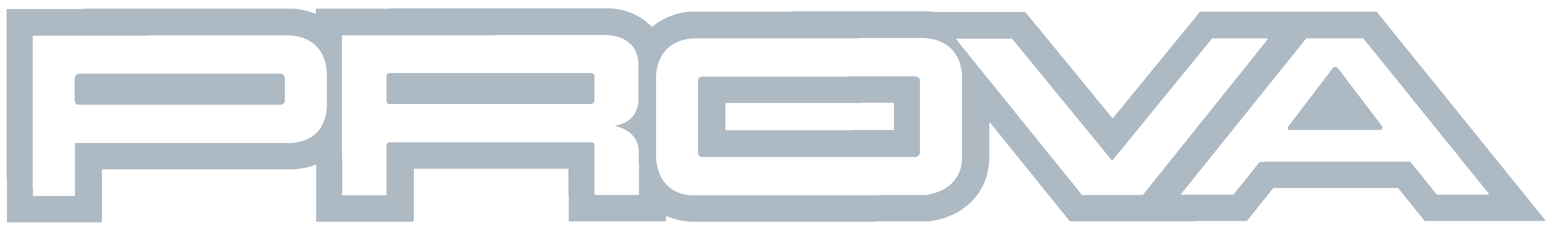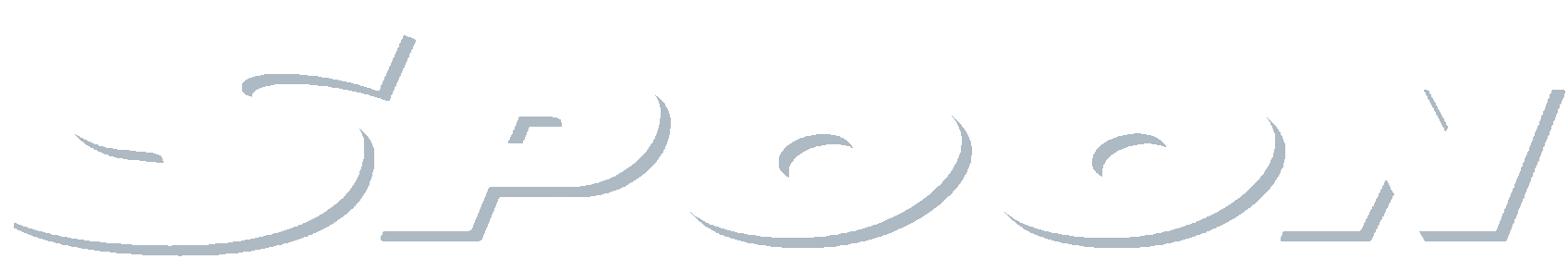こうして無事に本日の作業は全て終了しました。
走行してみてステアリングのセンターが狂っている場合は絶対に必要ですが、無ければとりあえず当面はアライメントを取り直す必要はないだろうとのことでした。
それにしても、作業を終了したのは午後4時過ぎでしたので、昼食も摂らずにぶっ通しの5時間という長丁場となってしまいました。
それでも駒田社長は「だいたい予想していました」と涼しいお顔でした。
本当にお世話になりありがとうございました!!
その効果はといえば、帰路で真っ先に気付いたのですが、なんと格段に乗り心地が良くなっていました。
なぜだか理由はよくわかりませんが、それは紛うこと無き事実です!!
また後日改めてじっくりインプレッションしたいと思います。
特にリジカラを装着しているボルトは、感触を確かめるようにしながら、慎重に締め込んで仮止めしました。(フロントカラー部)
そこで一旦仮止めしていたサブフレームのボルトを、再び緩める必要が出てきました。
ところが右側のリジカラ挿入ボルトは、フレームとのねじ穴のセンターが若干ズレていました。(右フロントカラー部)
そのままねじ込むとリジカラのスペーサー部分を押しつぶしてしまう危険性が高かったので、左右の各ボルトを必要に応じて緩めたりしながら、サブフレームの取り付け位置を微調整した結果、確実に挟み込むことが出来ました。(右フロントカラー部)
これも一旦仮止めしました。
これで間違いないと、もう一方の左側のボルトも緩めました。
案の定作業に必要な隙間が、フロントカラー部に3㎝ほど確保出来ました。
そこでサブフレームの後部の樹脂製のカバーを取り外して、もう一本のボルトも緩めることにしました。
この時、まだサブフレームは後部に左右2本づつボルトが残っていまして、その内の前側のボルト2本がしっかり効いているので、隙間が確保出来ないものと考えました。
ホイールを元に戻しました。
これが最もトルクの掛かっているボルトです。
STi製ロワーアームバーを共締めしています。
ところがいざ作業に取り掛かってブッシュを固定しているボルトを外そうとすると、どうしてもフレームの壁に阻まれて抜き取ることが出来ません。
そこでこの作業は取り止めました。
後日取り付け方法をDラーで確認することにしました。
兎に角、見ていても実にしんどい作業がこうして無事に終了しました。
予め二分割しておいた黄○印のカラーの半分にグリスを塗布します。(メインカラー部)
手前に見える黒いのがフロントクロスメンバーです。
この位置からですと、隙間の有無がよく判りませんね。
早速固定ナットを取り外しました。
その作業の様子は、私が駒田さんの作業をし易くするために、ステアリング操作をしていたために、残念ながら撮影出来ませんでした。
次に作業の邪魔になるフロントホイールを取り外しました。
狭い隙間でほとんど手探り状態ですが、しっかりセット出来ました。(フロントカラー部)
サブフレームとフレームの間にに出来た隙間に挟み込む赤○印のカラーに、付属していたグリスを塗布しました。(フロントカラー部)
次にカラーをセットしない他のボルトを抜き取っていきます。
青○印のカラーを使います。(フロントカラー部)
朝10:30にGRANDSLAM FORMに到着し、しばらく待って11:00ごろに作業が始まりました。
ステッカーも付属していました。
取説も同梱されています。
早速箱を開けて中身を確かめました。
フロントサポートバーにアルミアンダーパネル後部のブラケットを取り付けました。
2015年3月7日
本日は GRANDSLAM FORMで、コレを注文してきました。
以前から気になっていました、PROVA(spoon製)リジッドカラーです。
巷ではその効果を疑問視する声もあるようですが、実際に装着してみなければ始まりませんので、駒田社長にいろいろ調べて頂いて、とりあえずフロントメンバーとサブフレーム用のキットを装着することにしました。
因みにリアは、spoonよりGC8用としてリリースされているものが装着可能。
効果のほどは後日インプレッションしたいと思います。
続いてフロントロワアームバーを共着しているボルトを取り付けました。
こうして4箇所全てのリジカラがセット出来ました。(メインカラー部)
実際には、こうして樹脂製のヘラを使ってずらしています。
所定の位置にセット出来たか確認するために、メンバーのボルト穴を下からのぞき込んで、スペーサー部分が確実に穴とボルトの隙間にあるかを確認しました。(メインカラー部)
このボルトにカラーをセットします。(フロントカラー部)
抜き取ったボルトにカラーをセットしました。(フロントカラー部)
ホイールナットの締め込みは、もちろん持参したトルクレンチで行いました。
アルミアンダーパネルを取り付けました。
ここでコレを取り出して、早速換装することに…
フロントアルミアンダーパネルのブラケットを共締めしているボルトを仮止めして、ブラケットを取り付けました。
右側です。
そして、最後の2本を指定トルク7.2㎏/m,±0.5(71Nm,±5)で締め込んで、樹脂製カバーを取り付けました。
また、かつて私はこのRA-Rを購入した当初、重いこのサブフレームを取り外して、軽量なアフターパーツメーカーのものに交換しようかと考えたこともありました。
しかし後に、C's MARCHE の桑原氏のこの記事を読んでいたく共感し、考え直しました。
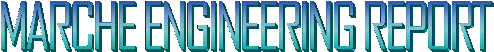 以来、取り外さずに今に至っていますが、これはいろんな意味で正解でした。
以来、取り外さずに今に至っていますが、これはいろんな意味で正解でした。
このボルトの指定トルクは、フロントクロスメンバーと同じ10.7㎏/m,±0.5(105Nm,±5)です。
左側
最初ボルトを取り外したときと比べると、やはりかなり緩い感じです。
後日、三重スバル四日市店のメカニック倉田さんからお聴きした話ですが、確かに以前このサブフレームのボルトを増し締めしてはいただいたのですが、それほど無茶なトルクで締めたわけでは無かったようです。(確か60㎏/m程だったような記憶が…)
実はその事が今回サブフレームのボルトを緩める際に、高トルクが必要になった要因ではなく、もともとこのボルトは既定のトルクで締めてあっても長期間緩めずに置くと、ボルトの固着等で緩めるには相当の力が必要になるんだそうです。
右側のリジカラセットボルトです。(フロントカラー部)
サブフレームの前両側3本づつ計6本のボルトは、メーカー指定トルクは5.6㎏/m,±0.5(55Nm,±5)でしたが、ちょっと頼りないので少し増し締めしました。(約6㎞/m)
この先頭のボルト左右一対にリジカラがセットされています。(フロントカラー部)
これは左側(フロントカラー部)
サブフレームも全てのボルトナットの仮止めが終わり、続いてメーカー指定トルクで本締めします。
駒田社長も私も老眼で役に立ちませんので、若い息子さんがトルクレンチの目盛りをセットしています。(笑)
これはまだ仮止めです。
この後メインカラー部のフランジナットは、トルクレンチ(メーカー指定トルク10.7㎏/m,±0.5(105Nm,±5))で本締めを行いました。
フロントクロスメンバーのナットは、用意していた新品の純正セルフロックフランジナットを締め込みました。(メインカラー部)
左側のボルトも同様に…(フロントカラー部)
後は緩めてあったサブフレームの全てのボルトを再び締め込んで仮締めします。
やりとりを聴いていると、お二人の息がピッタリ合っていて、流石は親子だと感心しました。(メインカラー部)
ここからは2人がかりで作業しました。
従業員の息子さんがホイールハウス側からクロスメンバーのボルト穴を下から覗いて修正指示を出し、駒田さんがそのナビゲートに従って上からカラーをセットするというコンビネーションです。(メインカラー部)
このフロントクロスメンバーは、フレーム側からボルトが出ていますので、隙間が出来てもカラーは半分づつしかセット出来ません。
まず半分を手前から差し込んでセットした後、ボルトの反対側にずらして回り込ませます。
スペーサー部分が穴から外れないようにしてずらすのは、この狭いスペースではなかなかしんどい作業です。
上手くボルトの反対側にセットできたら、次にもう半分を同様にセットします。
但し、注意しなければ行けないのは、2枚が重ならないようにすることが重要です。(メインカラー部)
ホイールハウス側からは良く判ります。
ギリギリで指が入る程度の隙間が出来ました。
何が要点かと申しますと画像の黄色い矢印の部分、フロントクロスメンバーの左右両端の部分(これは右側)が見えていますが、これがリジカラを挿入出来るところまで下がらないといけないわけで、最低でも5㎜以上の隙間が必要です。(メインカラー部)
これは続いてサービスマニュアル通り、ステアリングシャフトのユニバーサルジョイントを緩めるために、駒田さんの指示に従ってステアリングを切っている様子です。
後でユニバーサルジョイントを繋ぐとき、センターがズレては大変ですので、この作業は慎重に行っています。
これでホイールハウス側からフロントクロスメンバーの固定ナットの目視が容易になりました。
このナットを取り外して、フロントクロスメンバーとメインフレームの間に、隙間を確保しなければなりません。(メインカラー部)
他のボルトも仮止めしました。
これは取りあえず仮締めをしました。(フロントカラー部)
そこに慎重に青○印のカラーをセットしたボルトを差し込んで、フレームにねじ込みました。(フロントカラー部)
この左側のボルトは、センターがズレたりするような問題は無く、赤○印のカラーを上手く挟み込めました。(フロントカラー部)
樹脂製のカバーを外して、現れたボルトを緩めました。
するとリジカラ挿入部の隙間が少し広がりました。
またフロントサポートバーに取り付けているアルミアンダーパネル後部のブラケットも、そのままではフロントロワアームバーが引っ掛かって、サブフレームを引き下げることが出来ませんし、フロントロワアームバーをサブフレームから取り外すことも出来ません。
従ってリジカラをサブフレームとフレームの間に挟み込むための隙間を確保するためには、このブラケットも取り外さなければなりませんでした。
しかしこれでもまだ必要な隙間の確保は出来ませんでした。
フロントアルミアンダーパネルのフロントブラケットを共締めしている、サブフレーム左フロントブラケット部のボルトも抜き取りました。
因みにサブフレーム右フロントブラケットは、2006年8月から廃止されています。
実際、ボルトごとに正確に締め付けトルクが指定されているのに、何故緩めるときにはこれほど強い力が必要なんでしょうか?
このようにレンチのアームを延長しなければならないほど…
実は理由は忘れましたが、過去にスバルのDラーで、このサブフレームのボルトを増し締めしていただいたのですが、硬く締まったボルトを緩めるのに相当力が必要でした。
さしあたって、サブフレームのリジカラ装着ボルトから抜き取りました。(フロントカラー部)
まずアンダーパネルを取り外しました。
リフトアップ
リジカラ専用のグリスが同梱されていました。
これは後で判ったことですが、中身は私が以前から使用して重宝しているPROVAから購入しました、COPASLIPと同じ物だと思います。
向かって左側の上の赤○印の二つがサブフレームとフレームの間に挟み込むカラー(フロントカラー部)で、下二つがサブフレームの下側にセットするカラーで、上下ワンセットになっています。
一方右側の黄○印の四つは、フロントクロスメンバーとフレームの間に挟み込むカラー(メインカラー部)で、それぞれ二分割出来るように割が入っています。
正直、こんな小さなパーツにどれほどの効果があるのかという印象です。
2015年4月7日
GRANDSLAM FORMに PROVAリジッドカラーを注文してから丁度1ヶ月経ったこの日、取り付けに訪れました。
このロックナットと共に、以前にネットで購入し、この日到着しました、とあるパーツを後日GRANDSLAM FORMに預けてきました。
当初、スグに入荷すると思っていましたリジカラの在庫が無く、随分待ちましたがこのほどやっと入荷日が決まりました。
4月7日、装着予定です。
購入してきました。
セルフロックナットです。
2013年3月12日
フロントメンバー固定ナットがセルフロックナットであることが判明しましたので、この日三重スバル鈴鹿店で品番を確認して在庫を調べていただきました。
四日市の部品センターに、丁度在庫があるということでしたので、その足で早速部品センターへ赴きました。
こちらのサブフレームは、全てボルトによって固定されていました。
リジカラ装着について、ちょっと事前学習を行いました。
電子パーツカタログSUBARU-FASTⅡ A-1版にてチェックしましたところ、フロントメンバーの固定ナットはどうやらセルフロックナットであることが判明しました。
再使用が出来ませんので、後日購入することに…
こうして外から見えているサブフレームのボルト(9本)は全て緩めるか抜き取りました。
しかしこれでも、リジカラを挟み込むための隙間は全然確保出来ませんでした。